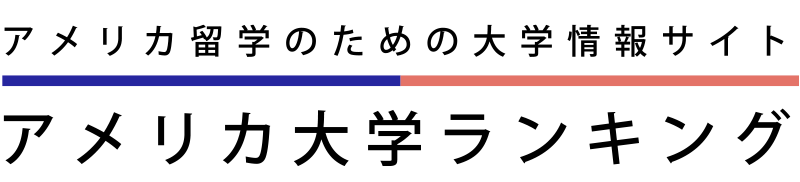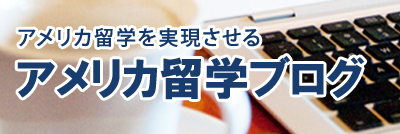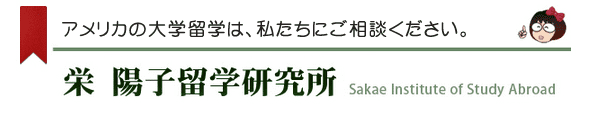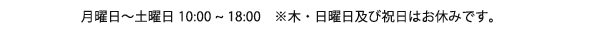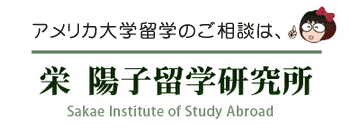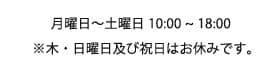アメリカ留学生活がスタート! 怒涛の1週間をレポート
こんにちは。週末の朝は意識して日本の本を読むようにしている、まなみです。アメリカの大学では、勉強やその他のアクティビティが忙しく、最近まで日本の本を読んでいませんでした。とくに留学して1年めは「友だちをつくらなきゃ」と毎日気合を入れていたので、なるべく1人ではご飯を食べないようにしていました。
今年は「自分への投資」を目標にしているので、週末はカフェテリア(学生食堂)で本を読みながらブランチを食べています。
留学して2年目になると自分の中での変化に気づきます。
今回は、ガツガツしていた入学当初の私を振り返りたいと思います。

もくじ
1.留学生のためのウェルカムファミリー
1-1.大学から家族をもらう?
1-2.ホストペアレンツが2人とも留学経験者
1-3.家の鍵をあげるから・・・
2.留学生だけのオリエンテーション
2-1.留学生同士だからわかり合える
2-2.名前当てゲーム
3.アメリカ人学生がキャンパスに到着
3-1.First Year Seminar
3-2.アドバイザーの存在
3-3.いよいよ履修登録
4.留学生は「強い」
1.留学生のためのウェルカムファミリー
私が留学している大学は、入学前から、留学生のサポート体制がしっかりしています。とくに「ウェルカムファミリー」制度は、私の留学生活の中で欠かせないものです。
1-1.大学から家族をもらう?
ウェルカムファミリーとは、大学が留学生のために準備してくれる家族です。基本的には、大学の卒業生か先生がウェルカムファミリーになります。9月に入学する前の夏休みに家族の情報がメールで届き、その後やりとりをしました。私にはホストファミリーとの苦い経験があったので(この記事を参照してください)、正直「え、必要ないかも」と思っていました。
ウェルカムファミリーとの出会いは突然でした・・・すみません、ちょっとカッコつけました。実際は、ワシントンからの長いドライブだったため、車内で爆睡していました(笑)。そのため、「あの人たちじゃない?」と起こされて5秒ほどしか心の準備ができませんでした。出会いが突然すぎて、記憶にありません。
1-2.ペアレンツが2人とも留学経験者
初めは「何か話さなきゃ」と緊張していましたが、だんだん家族のことがわかり、2日目には居心地のよさを感じました。理由は大きく2つあります。1つ目は、家に3匹の犬がいて、週末は野良犬のレスキューをするほど犬好きな家族だったからです。
私も犬が大好きなので、すぐに打ち解けました。
そして2つ目は、家族に留学経験があったからです。お父さんもお母さんもドイツに留学していたので、留学生の気持ちをわかってくれました。私が何を理解していなくて、どうしたら伝わるのかを考えながら、とても慎重に、ていねいに話してくれました。
日本に行ったときの写真を見せてくれたり、ジョークを「そこまでこと細かに説明したら逆におもしろくないじゃん」というくらい掘り下げて(紙に書いたりもして)説明してくれたり、私がホストファミリーに求めていたすべてがそろった家族でした。この家族の素晴らしさを挙げるとキリがありません。
1-3.家の鍵をあげるから・・・
この家族との2日間はあっという間でした。この家族が大学に依頼されたことは、
・大学生活に必要な買い物のお手伝い
・オリエンテーション会場までの移動
・大学の寮への荷物運びのお手伝い
です。でも私は、それ以上のことをしてもらいました。映画や日本食レストランに行ったり、犬と遊んだり・・・最高の2日間でした。
ついに「家の鍵をあげるから自由に出入りしていいよ」と言ってもらえるまでの信頼関係を結ぶことができました。
私の実の母と会ったときに、「まなみをこの大学に送り出してくれてありがとう。私たちはまなみの家族になれて本当に嬉しい」と言う姿を見て「私は、幸せだ」と心から思いました。
最近は、シアターの練習が忙しくてなかなか会えていません。いつか大きな恩返しをしたいな、いや、しようと思っています。この文章を書来ながら会いたくなってきたので、いまから連絡しようと思います。
2.留学生だけのオリエンテーション

大学から指定されたオリエンテーション会場にウェルカムファミリーと行くと、すでに何人かの留学生が集まっていました。留学生向けのオリエンテーションが始まります。
2-1.留学生同士だからわかり合える
私の大学は総学生数が約600人に過ぎません。留学生の数も少ないです。私と同じ年に入学した留学生は、私を含めて6人。オリエンテーションでは、留学関係のオフィスで働く人と、Mentorと呼ばれる2年生以上の留学生の先輩がさまざまな企画を準備しています。
このオリエンテーションの大きな目的は、留学生同士の絆を深めることです。留学生といっても、アメリカ人の学生と同じくらい英語が話せる人もいます。それでも、なんとなく新しい生活に馴染めなかったり、ホームシックで泣いてしまう子もいます。そんなときに留学生同士だと、わかり合える場面が多いのだと思います。
私は基本的にグループに属さないタイプなので、留学生のみんなといつも一緒にいるわけではありません。でも留学生は、話したいと思ったときに、いつでも戻ってこられるグループだと思っています。
ちなみにMentorとの関係は1年間続きます。毎週月曜日に集まり、留学生にとって大事な情報を共有したりします。私も今年はMentorとしてかかわっています。
2-2.名前当てゲーム
オリエンテーションでは、・自己紹介
・キャンパスツアー
・大学のルールの説明
・銀行口座のつくりかたの説明
などが、3日かけて行われました。
また、名前を覚えるための「名前当てゲーム」が頻繁にあり、名前を覚えるのが苦手な私は毎回胃が痛くなっていたことを覚えています。
私が3日間を通じて思ったことは「すべてが少し子どもっぽい」でした。「これって大学生がすること?」と思う内容のゲームが多かったり、「それって当たり前じゃない?」と思う内容のディスカッションが多かった記憶があります。
これはオーストラリアに短期留学していたときも感じたことなので、あまり驚きませんでした。マインドセットが早い私は「日本じゃないから恥ずかしくない。全力で子どもっぽさを楽しもう」と思い、高校生になったつもりで過ごしました。
3.アメリカ人学生がキャンパスに到着
とうとう、アメリカ人の学生が大学に到着する日がやって来ました。ガラガラだったキャンパスにもポツポツと人が現れます。
3-1.First Year Seminar
私の大学にはFirst Year Seminar と呼ばれる科目があります。全員が1年生の科目です。1年生がいくつかのクラスに分かれるのですが、クラスごとにテーマが与えられます。私のテーマは、 “How to Be a President.”でした。英語もよくわかっていない留学生に大統領になるための勉強をさせるなんて・・・「大学もなかなか攻めるな」と思いました(笑)。
このFirst Year Seminar は、単位をもらえる普通の科目です。しかし、他の科目と違うところがたくさんあります。
たとえば、オリエンテーション期間はこのクラス単位で集まり、アイスブレイクやディスカッションをします。ダウンタウン散策や月に1度のミーティングも、このクラス単位で行います。また、1つのクラスに上級生が2人お世話をしてくれます。1人はオリエンテーション中のサポート、もう1人はFirst Year Seminar の授業や授業の登録のお手伝いをしてくれます。

3-2.アドバイザーの存在
そして、忘れてはいけないのがアドバイザーです。アドバイザーとは、学生のアカデミックなサポートをしてくれる先生のことです。
私の場合は心理学専攻なので、心理学の先生がアドバイザーとなり、科目を選んだり卒業後の進路を決めたりする際に相談に乗ってくれます。
でも、リベラルアーツ・カレッジの1年生は、専攻を決めていない場合が大半です。そのため1年生に対しては、First Year Seminarの先生がアドバイザーになります。
私は、”How to Be a President”のクラスにとても苦しめられていました(笑)。トランプさんとヒラリーさんが激戦を繰り広げているときにこのクラスをとってしまい、白熱する議論についていけず、いまでも一番ついていくのが大変だったクラスだと思っています。そのため、このSeminarの先生が私のアドバイザーでよかったと思った場面が多くありました。
3-3.いよいよ履修登録
アメリカの大学のキャンパスに着いて最初の1週間での大きなイベントといったら、履修登録(Course Registration)です。エクセルにある一覧を見て科目を選び、インターネットで登録します。初めはどの科目をとったらいいのかわからずパニックです。卒業までの必須であるライティングやプレゼンのクラスをとるべきか、楽しそうなクラスをとるべきか、とても悩みます。私も専攻が決まっていなかったので、どの科目をとるべきかまったくわかりませんでした。
いま、私ができるアドバイスは2つです。
まずは「周りの学生に授業の内容を聞く」こと。上級生に授業の難易度や課題の量を聞くことによって、絶対にとりたくない授業を消していきます。
そして2つめは「少し多めの科目を登録する」こと。
じつは、アメリカの大学には科目の追加と削除ができる期間があります。その際、削除のほうが追加よりも簡単です。なぜなら追加の場合は、その時点でみんなが受けてきた授業の復習をしなくてはならないからです。
私も何度もこの期間に科目を減らし、調整してきました。
もちろん、とりすぎはダメですが、とろうかどうか悩む科目がある場合は、とってみて様子を見るのも大事だと思います。
私は留学1年目から乗馬とシアターにかかわってきました。アドバイザーに「乗馬とシアターは多すぎる」と言われましたが、「できる」と言いきり登録しました。やりたいことはやるべきです。
自分は周りから反対されたほうが、燃えるタイプなんだと思います。
ちなみに、履修登録は早いもの勝ちです。時間になるとみんながパソコンにかぶりついてカチカチしています。慣れるまでは、なかなかストレスフルなプロセスになると思います。
4.留学生は「強い」
留学生活が始まって最初の1週間は、新しいことの連続でとても疲れます。情報量も多く、すべてを理解し把握するのは不可能です。
わからないことはわかるまで聞くことが大事です。
でも、たまには「多分わかった」くらいでもいいと思います。
「自分の国を出てアメリカに来るなんて、すでにみんなは強い」これは留学生のオリエンテーションでオフィスの人から何度も言われた言葉です。
たまには自分に優しくしながら、淡々と目の前のことをこなせば、「怒涛の1週間」もあっという間です。
まなみさんの記事一覧
・第1回 そうだ、留学しよう
・第2回 私を大切にしてくれるアメリカの大学を探して
投稿日:2018年04月07日(Sat)
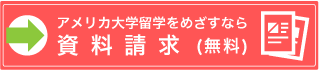
【あわせて読みたい関連記事(現在は最新記事のみ最大5件載せています)】

留学のプロがおすすめしないアメリカ留学の方法

アメリカ留学をおすすめしない理由。治安? 人種差別? 費用?

名前に「カレッジ」とつく大学ってみんな短大なの?

アメリカ留学中のおすすめアルバイト

アメリカの大学に留学するのに、ビザ申請ってどうすればいいの?