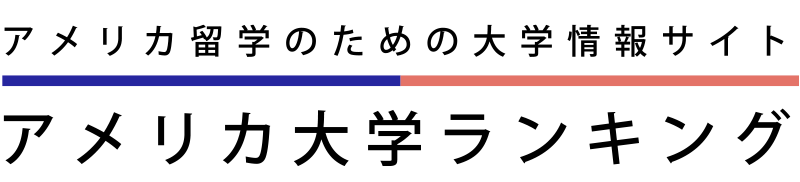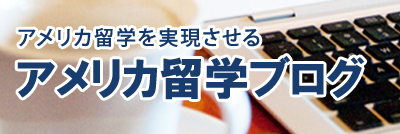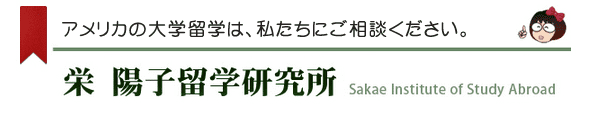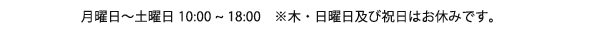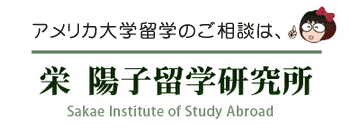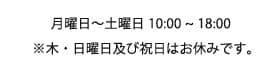アメリカ留学を映画で予習! 落ちこぼれたちのリターンマッチ 『ヤング・ゼネレーション』
みなさんこんにちは! アメリカ留学ラボのカイトです。このラボでは、アメリカの大学に留学したい!という人のために、知って得する話題や役に立つ情報をお届けしています。今回は、「アメリカ留学を映画で予習する」シリーズとして、『ヤング・ゼネレーション』(1979年)という映画をご紹介します。といっても、この映画の主人公では大学生ではなく、大学に行きそびれてしまった、いわば落ちこぼれの青年です。
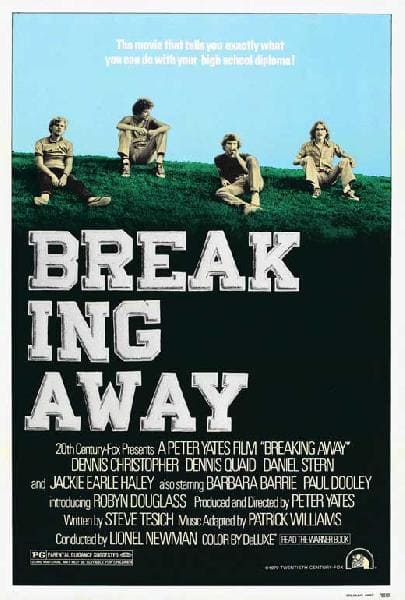
アメリカ有数の大学町が舞台
映画の舞台はインディアナ州のブルーミントン(Bloomington)。ここはインディアナ大学ブルーミントン校という州立大学のお膝元で、全米有数の学園都市です。同大学は学部生と大学院生をあわせて4万人以上を抱えるマンモス大学で、インディアナ州の州立大学の中では最もレベルが高く、しばしば「パブリックアイビー」の1校として取り上げられます。映画は、ブルーミントンの地元っ子である4人の青年が、ダムのようなところ(かつての石切場)で遊んでいるところから始まります。彼らは高校を卒業して1年が過ぎようとしているのに、大学に進学もせずにブラブラしています。
そんな仲良し4人組のうちの一人デイビッドがこの映画の主人公です。彼が最近ハマっているのは自転車とイタリア。彼のお父さんはデイビッドの現状にかなりの不満と心配を抱いていますが、このお父さん自身、かつて採石で腕を鳴らした昔を懐かしむばかりで、威厳が感じられません。

地元の落ちこぼれvs大学生
4人組のお気に入りの場所が、冒頭から繰り返し描かれる石切場です。じつはインディアナ州は石灰石の産地として名を馳せてきた歴史があって、インディアナ大学ブルーミントン校の学舎の多くも、地元の石灰石でつくられた経緯があります。この石切場がとても印象深く、また美しく描かれています。デイビッドたち4人組は、いずれは人生の次のステージに踏み出さなければならないことを、なんとなく自覚しています。いつまでも仲良し4人組ではいられない、という焦りも感じています。それだけにあたかも1歩先に自らの人生を切り開いているかに見える大学生たちに、激しい嫉妬心と競争心を抱いています。

大学キャンパスで喧嘩と恋愛
それで彼らはインディアナ大学ブルーミントン校のキャンパスに赴いては、学生に喧嘩をふっかけたり、ふっかけられたりを繰り返します。同大学のキャンパスが何度も出てきますが、これは実際のインディアナ大学ブルーミントン校のキャンパスです。エキストラも同大学の学生たちだそうです。このキャンパスの描写には、とても説得力が感じられます(この映画は、全体的に撮影がすぐれています)。デイビッドは自分をイタリア人だと偽って、キャサリンという女子学生にアタックし、どうやら成功しそうです。彼はキャサリンが住んでいるソロリティの「ハウス」の前で、イタリア語でアリアを歌って告白するのですが、ハウスについては以前に書きましたので、その記事をご参照ください。アメリカのキャンパスムービーには、とかくフラタニティやソロリティが出てきますね。

勝負は自転車レースで
一方で、4人組と大学生との衝突は激しさを増すばかりで、とうとう学生食堂での大乱闘にまで達します。大学生たちは、石切職人の息子たちである彼ら地元っ子のことを“Cutter”と呼んで軽蔑します。この辺りは、かつての栄光に引きずられているデイビッドのお父さんの屈折した感情にも結びついています。大学当局は、たび重なる衝突に業を煮やして、“Little 500”という自転車レースで正々堂々と勝負することを提案。ここから映画はクライマックスに向います。
Little 500とは、実在する自転車レースのことで、インディアナ大学ブルーミントン校の競技場で行われます。インディ500という、やはりインディアナ州で行われる自動車レースの自転車版とでもいうものです。4人一組になってトラックを200周し、順位を競います。この興行による収入は、学生の奨学金にあてられるそうです。
デイビッドたち4人組は自らのチームを“Cutters”と名乗り、レースに挑みます。結末は、まあ予想通りですのでここで述べても差し支えないと思いますが、デイビッドの大活躍があって、Cuttersが優勝。落ちこぼれ4人組は見事に雪辱を果たしたことになります。このシーンでの観客席には、インディアナ大学ブルーミントン校の第11代学長で、大学の発展に大きく貢献したハーマン・ウェルズ氏の姿も見られます。ウェルズ氏は、同大学にウェルズ図書館として名を残しています。

大学の入学試験?
ところでデイビッドは、このレースの前にインディアナ大学ブルーミントン校の入学試験を受けていて、それをパスしていました。映画のエンディングではデイビッドは大学生になっています。この「入学試験」、セリフでは“College Entrance Exam”となっています。まさに入学試験としか訳しようのない言葉で、日本語字幕もそのように表記されています。でも、アメリカの大学についてご存知の方は、オヤッと思うのではないでしょうか。というのも、アメリカの大学にはいわゆる「入試」は存在せず、高校の成績やエッセイ、推薦状などの書類審査で合否が決まるはずだからです。
たしかに現時点では、インディアナ大学ブルーミントン校に入試は存在しません。この映画における入試とは、映画がつくられた当時(1979年頃)にはそのような試験が存在したか、あるいはCLEPと呼ばれる全米標準のテストを指すのか、いずれかだろうと思います。この事情はよくわかりませんので、ご存知の方は教えてくださいm(-_-)m。
映画の原題はBreaking Away。この場合は「抜け出すこと」といった意味です。自転車レースで抜き出ること、そしてこれまでの仲良し4人組の生活から抜け出すこと、さらに父親の世代の栄光の影から抜け出すこと、という三重の意味が込められているように思えます。
この映画は、アカデミー賞の脚本賞を受賞し、ほか4部門でもノミネートされました。脚本を書いたスティーブ・テシック氏は自身がインディアナ大学ブルーミントン校の卒業生で、実在のモデルや実際に起きたエピソードが脚本に盛り込まれているそうです。
『ヤング・ゼネレーション』はいまでも名作の呼び声が高く、アメリカの「大学映画」の代表作の一つです。2006年には、アメリカ映画協会(AFI)による「最も勇気づけられる映画ベスト100」で見事8位に選ばれました。この映画が長く愛されていることがうかがえます。興味をおもちのかたはぜひご鑑賞ください!
アメリカ大学ランキングでインディアナ大学ブルーミントン校を調べてみる!
投稿日:2016年01月25日(Mon)
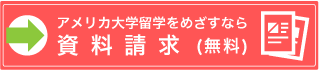
【あわせて読みたい関連記事(現在は最新記事のみ最大5件載せています)】

留学のプロがおすすめしないアメリカ留学の方法

アメリカ留学をおすすめしない理由。治安? 人種差別? 費用?

名前に「カレッジ」とつく大学ってみんな短大なの?

アメリカ留学中のおすすめアルバイト

アメリカの大学に留学するのに、ビザ申請ってどうすればいいの?